
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
節分に食べるものといえば恵方巻ですよね。
黙って一本食べきると幸福になるといわれている恵方巻ですが、その由来・ルーツをご存じでしょうか?この記事では
恵方巻の発祥・歴史を紐解き、誰がいつ流行らせたのかを解説していきます。恵方巻・太巻きの違いもお伝えしますね。
2024年の恵方巻きの方向は「東北東」

節分に食べるものと言えば、恵方巻ですね。毎年、恵方を向きながら食べている人も多いのではないでしょうか? この毎年
「恵方巻」を食べるために向いている方向のことを、恵方と言います。この恵方は歳徳神という神様がいる場所とされており、
「その年の中でも特に縁起のいい方角」とされています。そのため、かつては初詣も恵方の方向の神社に参ったり、初めてのことを行う時は恵方に向かって行ったりしていたそうです。
恵方巻きの由来
実は恵方巻の由来について、定説はありません。有力な起源とされているのは2つあります。
ひとつは大正時代から戦後にかけての間、大阪を中心に関西で節分に行われていた行事です。関西では節分に芸遊びをしながら商売繁盛をお祈りする際に、「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」を食べていたことが始まりとされています。
もうひとつは、1973年頃、大阪海苔問屋協同組合が寿司店と手を組んで、節分に「太巻き寿司」を「恵方巻」として売り出したことが始まりとも言われています。その後、1998年に大手コンビニが海苔巻きを販売する際に、恵方巻として大々的にPRをした結果、全国に広まりました。
恵方巻と太巻きは別もの?
恵方巻と太巻きは、どちらも巻き寿司の一種です。恵方巻は前述の通り「節分に食べる巻き寿司」や行事そのものを指す言葉で、太巻きは一般的に「複数の具材が入った、通常より太い巻き寿司のこと」を指します。
つまり、巻き寿司が「具材を巻いた寿司の総称」で、そのなかに「太巻き」「恵方巻」という種類があるということですね。
太巻き・恵方巻は、巻き寿司の別名ともいえます。
恵方の決め方
 恵方は、歳徳神という神様がいる場所
恵方は、歳徳神という神様がいる場所です。この歳徳神がいる場所は毎年変わるため、恵方もその度に変わります。それでは、この恵方は一体どうやって決まっているのでしょうか?
実は恵方は、基本的にの4つ
恵方は、基本的に「東北東」「西南西」「南南東」「北北西」の4つしかありません。この向きはその年の「十干」と組み合わせることで決めています。
十干とは、十二支のようなものです。中国から伝わったものであり、「甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)」の10通りで暦を表示しています。
十干は十二支と違って一般的ではないため、関連づけて覚えるのは難しいですよね。実は、恵方は西暦の1の位でも確認をすることができます。
西暦の1の位が「0、5」の年は「西南西」、「1、3、6、8」は「南南東」、「2、7」は「北北西」、「4、9」は「東北東」となっています。覚えておくと便利ですね。
2024年はいつ食べる?恵方巻きの正しい食べ方
 2024年は2月3日(土)
2024年は2月3日(土)
恵方巻は
節分の日に食べるものです。そのため、2024年は2月3日(土)に食べます。
節分は2月3日と思っている方も多いのではないでしょうか。実は、節分は2月3日と決まっているのではありません。節分は旧暦の正月にあたる立春の前日です。立春は2月4日というイメージが強いですが、決して決まっていることではありません。例えば2021年の立春は2月3日でした。過去30年の間で立春が2月4日ではなかったのはこの1回だけです。
2024年も立春が2月4日のため、立春の前日である節分は2月3日になります。
恵方巻きの正しい食べ方
恵方巻を
食べる際のポイントは3つあります。1つ目は、「切らずに食べること」。恵方巻は大きいため、食べやすいように切って食べたいと思う人も多いでしょう。しかし、恵方巻は切らずにそのまま食べる必要があります。これには、
「縁を切らない」という意味があります。
2つ目は「恵方の方向を向いて食べること」。恵方はその年の福をつかさどる歳徳神がいるとされている方向です。
その方向を向いて食べることで、縁起が良くなると言われています。
そして
3つ目が、「黙って願い事を思い浮かべながら食べること」。恵方巻は、1本を食べきるまで言葉を発してはいけません。これは
食べ終える前に言葉を発すると、運が逃げてしまうと言われているためです。黙って願い事を頭に浮かべながら食べることで、運が逃げず願いが叶うと言われています。
恵方巻を食べるときは、このような3つのポイントが大切です。福を招くためにも、これらのポイントをしっかり守って恵方巻を食べるようにしましょう。
恵方巻きの中身(具)は七福神と関係している

恵方巻は海鮮など、様々な食材が具材として使われていますが、一般的には7種類になります。この7種類は七福神と関係があるとされています。今回はその中でも3つの具材と関連する神様についてご紹介します。
恵比寿様ときゅうり
恵比寿様は七福神の中で唯一日本由来の神様であり、「商売繁盛」「五穀豊穣」をもたらす神様です。
「きゅうり」が「九の利を得る」に通じることから、恵比寿様と関連があるとされていますよ。
大黒天様とたまご
「たまご」の黄色が風水的に金運がアップすると言われていることから、関連する神様は財宝の神様である大黒天様です。大黒天様は「財宝」「福徳開運」の神様として信仰されています。
弁財天様とかんぴょう
弁財天様は、「音楽」や「芸術」、「縁結び」の神様です。
かんぴょうは江戸時代には「成分が美容にいい」と期待されていたことから、七福神の中で唯一女性の神様である弁財天様が関連していると言われています。
節分の日の過ごし方

節分は恵方巻を食べる以外にも様々な過ごし方があります。
豆まき
節分といえば「豆まき」。豆まきは一番奥の部屋から玄関に向けて、「鬼は外 福は内」という掛け声とともに豆をまく行事です。豆をまいた後は、自分の歳+1した数の豆を食べるようにしましょう。
柊鰯(ひいらぎいわし)
鬼は柊と鰯が苦手とされています。そのため、鬼(厄)が入ってこないように、焼いた鰯の頭を柊の枝に指した「柊鰯」という飾りを玄関に飾るという風習があります。
立春大吉
「立春大吉」は、立春に向けて運気アップをするための儀式です。立春大吉はすべての漢字が左右対称にできた、非常に縁起のいい言葉です。立春大吉と書かれたお札を玄関の表と裏に貼っておくと、無病息災の効果があるといわれています。立春大吉のお札を玄関に貼る時は、扉の右側に貼るとよいです。
恵方巻の定番具材のご紹介

恵方巻に入れる定番の具材は、縁起が良いとされている以下の7つの食材です。
・あなごやうなぎ
・えび
・しいたけ
・かんぴょう
・きゅうり
・桜でんぶ
・だし巻き卵
長寿の意味が込められているあなごやうなぎ、かんぴょうの他、語呂合わせから縁起の良いきゅうりやえびなど、それぞれの食材に願いが込められています。赤、黄色、緑と色鮮やかな見た目や、食感の違いも楽しめます。
まとめ
恵方巻についての解説はいかがでしたでしょうか。恵方巻は、節分の日に特定の方角を見て食べるものだとは知っていても、恵方の決め方は知らなかったという方も多いのではないでしょうか?
恵方は「非常に縁起のいい方角」とされているため、節分だけでなく何か物事を始めるときには恵方を向いて行うといいとされています。また、恵方巻は七福神と関連があるとも言われている縁起のいい食べ物です。2024年の節分は縁起を担ぐためにも、恵方巻を正しい食べ方で食べてみてください。
 こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
お花見での肉料理といえば、バーベキューが定番ですよね!簡単でおいしいけど、毎回お肉を焼くだけでは飽きてしまいませんか?そんな方は、ちょっと凝った肉料理オススメです!今年試したくなる、お花見バーベキューにおすすめのお肉料理を紹介します。バーベキューは、いつもより豪快な料理が作れるので、お肉料理との相性は抜群です!
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
お花見での肉料理といえば、バーベキューが定番ですよね!簡単でおいしいけど、毎回お肉を焼くだけでは飽きてしまいませんか?そんな方は、ちょっと凝った肉料理オススメです!今年試したくなる、お花見バーベキューにおすすめのお肉料理を紹介します。バーベキューは、いつもより豪快な料理が作れるので、お肉料理との相性は抜群です!

 肉や野菜を焼いて食べるのが定番のバーベキューですが、新しいレシピに挑戦してみたいという方も多いのでは?今回は、定番料理はもちろん、おすすめのお手軽料理をご紹介します。焼き網のほかにアルミホイル、スキレットを使えばレパートリーが広がります。
肉や野菜を焼いて食べるのが定番のバーベキューですが、新しいレシピに挑戦してみたいという方も多いのでは?今回は、定番料理はもちろん、おすすめのお手軽料理をご紹介します。焼き網のほかにアルミホイル、スキレットを使えばレパートリーが広がります。
 キャンプやバーベキューで人気のスペアリブ!焼きたてあつあつにかぶりついて食べるスペアリブは、たまらないおいしさですよ。
前日にお肉以外の材料を混ぜ合わせておく。スペアリブの筋に切り込みを浅く入れ、ジップロックなどで30分以上よく絡ませて寝かせておく。当日は、そのまま網にのせ、中火でじっくり焼き上げるだけ!
キャンプやバーベキューで人気のスペアリブ!焼きたてあつあつにかぶりついて食べるスペアリブは、たまらないおいしさですよ。
前日にお肉以外の材料を混ぜ合わせておく。スペアリブの筋に切り込みを浅く入れ、ジップロックなどで30分以上よく絡ませて寝かせておく。当日は、そのまま網にのせ、中火でじっくり焼き上げるだけ!
 バーベキューで盛り上がること間違いなしの手軽な料理、カートンドッグを知っていますか?牛乳パックを燃やして作るホットドッグのことで、バーベキューにぴったりな料理です。具材を挟んだホットドッグをアルミホイルで包み、牛乳パックに入れる。そのまま牛乳パックに火をつけて、火が消えたら完成です!
バーベキューで盛り上がること間違いなしの手軽な料理、カートンドッグを知っていますか?牛乳パックを燃やして作るホットドッグのことで、バーベキューにぴったりな料理です。具材を挟んだホットドッグをアルミホイルで包み、牛乳パックに入れる。そのまま牛乳パックに火をつけて、火が消えたら完成です!
 定番ローストチキンは、まず味が染み込むよう肉にフォークなとで数カ所穴をあけます。しょうが、にんにくは薄切りにして、漬けだれの調味料と合わせてタレを作ります。密閉式ポリ袋などにタレとお肉を入れて一晩漬け込んで、網で焼きながら途中余ったタレをハケで何度か塗って焦げ目がついたら出来上がり!にんにくの香ばしさと、胡椒のスパイスがほどよくきいたメイン料理です。
定番ローストチキンは、まず味が染み込むよう肉にフォークなとで数カ所穴をあけます。しょうが、にんにくは薄切りにして、漬けだれの調味料と合わせてタレを作ります。密閉式ポリ袋などにタレとお肉を入れて一晩漬け込んで、網で焼きながら途中余ったタレをハケで何度か塗って焦げ目がついたら出来上がり!にんにくの香ばしさと、胡椒のスパイスがほどよくきいたメイン料理です。
 塩をつけていただくシンプルなサイコロステーキのご紹介です。一口サイズにカットしてから焼くので食べやすく、おつまみに最適ですよ!程よくサシの入ったサーロインはやわらかく、噛むほどに肉の旨みが感じられます。自然塩やトリュフ塩などで食べるのもおすすめです。
塩をつけていただくシンプルなサイコロステーキのご紹介です。一口サイズにカットしてから焼くので食べやすく、おつまみに最適ですよ!程よくサシの入ったサーロインはやわらかく、噛むほどに肉の旨みが感じられます。自然塩やトリュフ塩などで食べるのもおすすめです。
 肉汁をたっぷりと閉じ込めた、シンプルなハンバーガーです。パテに薄力粉をまぶすことで肉汁を閉じ込め、ジューシーなハンバーガーになります。ジューシーに焼いたパテにケチャップとお好みのドレッシングをかけて野菜を挟んだりと、ひと手間加えるだけで旨味が増しますのでぜひ試してみてくださいね。
肉汁をたっぷりと閉じ込めた、シンプルなハンバーガーです。パテに薄力粉をまぶすことで肉汁を閉じ込め、ジューシーなハンバーガーになります。ジューシーに焼いたパテにケチャップとお好みのドレッシングをかけて野菜を挟んだりと、ひと手間加えるだけで旨味が増しますのでぜひ試してみてくださいね。
 焼き豚は少々手間がかかりますが、十分に加熱したダッチオーブンに油を入れます。豚肩ロースを両面、焦げ色が付くまで良く焼いたら、用意した調味料を全て投入し、ふたをして弱めの中火で煮込む。途中肉をひっくり返しながら、1時間ほど煮込んで完成。そのまま食べても焼き豚丼などの具材にしても最高です!
焼き豚は少々手間がかかりますが、十分に加熱したダッチオーブンに油を入れます。豚肩ロースを両面、焦げ色が付くまで良く焼いたら、用意した調味料を全て投入し、ふたをして弱めの中火で煮込む。途中肉をひっくり返しながら、1時間ほど煮込んで完成。そのまま食べても焼き豚丼などの具材にしても最高です!
 たっぷりの野菜といただく、ヘルシー焼きしゃぶはどうですか。焼きしゃぶは、しゃぶしゃぶ用のお肉を軽く焼いて仕上げるだけの簡単料理です。薄いしゃぶしゃぶ肉を使うので、卵やポン酢でいただくと軽い仕上がりになりますよ。グリルプレートでさっと作れますのでぜひ試してみてください!
たっぷりの野菜といただく、ヘルシー焼きしゃぶはどうですか。焼きしゃぶは、しゃぶしゃぶ用のお肉を軽く焼いて仕上げるだけの簡単料理です。薄いしゃぶしゃぶ肉を使うので、卵やポン酢でいただくと軽い仕上がりになりますよ。グリルプレートでさっと作れますのでぜひ試してみてください!




 お問い合わせ
お問い合わせ
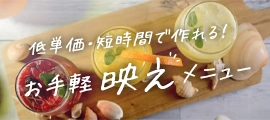














 こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
毎年3月3日は女の子の健やかな成長を願うひな祭りです。桃の花が咲く季節のため「桃の節句」とも呼ばれています。
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
毎年3月3日は女の子の健やかな成長を願うひな祭りです。桃の花が咲く季節のため「桃の節句」とも呼ばれています。


 ひな祭りにおすすめのメニューをご紹介します。定番のちらし寿司やはまぐりのお吸い物をはじめ、寿司ケーキや、いちごを使ったスイーツまで食卓が華やかになるレシピが満載ですよ。インスタ映えする盛り付け料理をご紹介していますので、ぜひチェックしてくださいね。
ひな祭りにおすすめのメニューをご紹介します。定番のちらし寿司やはまぐりのお吸い物をはじめ、寿司ケーキや、いちごを使ったスイーツまで食卓が華やかになるレシピが満載ですよ。インスタ映えする盛り付け料理をご紹介していますので、ぜひチェックしてくださいね。
 海鮮をふんだんに入れた、華やかなちらし寿司ケーキです。
海鮮をふんだんに入れた、華やかなちらし寿司ケーキです。

 手まりがモチーフのかわいらしいてまり寿司は、お子さまのひな祭りパーティーにぴったりです。
手まりがモチーフのかわいらしいてまり寿司は、お子さまのひな祭りパーティーにぴったりです。

 シャキシャキおいしいスナップえんどうで作る、ミモザサラダのご紹介です。
シャキシャキおいしいスナップえんどうで作る、ミモザサラダのご紹介です。

 春の香りを楽しむ、菜の花とベーコンのクリームパスタ。
春の香りを楽しむ、菜の花とベーコンのクリームパスタ。




 ひな祭りのお祝い膳にぴったり!上品な味わいのはまぐりのお吸物です。
ひな祭りのお祝い膳にぴったり!上品な味わいのはまぐりのお吸物です。
 かわいい見た目がひな祭りのデザートにぴったり!牛乳で作る苺のムースとカステラを重ねるデザートです。
かわいい見た目がひな祭りのデザートにぴったり!牛乳で作る苺のムースとカステラを重ねるデザートです。
 真っ白が可愛いらしい、やわらか白玉だんごはいかがでしょうか。
真っ白が可愛いらしい、やわらか白玉だんごはいかがでしょうか。
 こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
毎年3月下旬になると各地で桜が開花し、お花見の季節になります。今回はそんな
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
毎年3月下旬になると各地で桜が開花し、お花見の季節になります。今回はそんな お花見の始まりは、古くは平安時代の貴族が桜を見ながら歌を詠んだり、けまりをした行事が始まりで、次第に農民の間でその年の豊作を願って桜の下で宴会をするようになりました。
お花見の始まりは、古くは平安時代の貴族が桜を見ながら歌を詠んだり、けまりをした行事が始まりで、次第に農民の間でその年の豊作を願って桜の下で宴会をするようになりました。 お花見に欠かせないお花見弁当、今回は
お花見に欠かせないお花見弁当、今回は 桜の花を載せた可愛らしいおにぎりのご紹介です。
桜の花を載せた可愛らしいおにぎりのご紹介です。
 たけのこの食感が楽しい肉巻きメニューです。
たけのこの食感が楽しい肉巻きメニューです。

 アクセントのきいた菜の花のからし和え。茹でた菜の花を、
アクセントのきいた菜の花のからし和え。茹でた菜の花を、

 卵焼きはお弁当の定番ですが、洋風のオムレツ風にするのもいいですね。
卵焼きはお弁当の定番ですが、洋風のオムレツ風にするのもいいですね。

 見た目がかわいくて食べやすいチューリップチーズ手羽元を自分で作ってみませんか?難しそうに見えますが、
見た目がかわいくて食べやすいチューリップチーズ手羽元を自分で作ってみませんか?難しそうに見えますが、
 いつもとちょっと違う贅沢感のあるおにぎりなら、天むすもよさそう。えびに下味をつけ、塩味をきかせた衣をまとわせて油で揚げ、ご飯で包んで海苔を巻けば完成です。
いつもとちょっと違う贅沢感のあるおにぎりなら、天むすもよさそう。えびに下味をつけ、塩味をきかせた衣をまとわせて油で揚げ、ご飯で包んで海苔を巻けば完成です。
 フルーツとホイップクリームを挟んだフレッシュなサンドイッチ。
フルーツとホイップクリームを挟んだフレッシュなサンドイッチ。


 こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
節分に食べるものといえば恵方巻ですよね。
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
節分に食べるものといえば恵方巻ですよね。 節分に食べるものと言えば、恵方巻ですね。毎年、恵方を向きながら食べている人も多いのではないでしょうか? この毎年
節分に食べるものと言えば、恵方巻ですね。毎年、恵方を向きながら食べている人も多いのではないでしょうか? この毎年

 恵方巻は海鮮など、様々な食材が具材として使われていますが、一般的には7種類になります。この7種類は七福神と関係があるとされています。今回はその中でも3つの具材と関連する神様についてご紹介します。
恵方巻は海鮮など、様々な食材が具材として使われていますが、一般的には7種類になります。この7種類は七福神と関係があるとされています。今回はその中でも3つの具材と関連する神様についてご紹介します。
 節分は恵方巻を食べる以外にも様々な過ごし方があります。
節分は恵方巻を食べる以外にも様々な過ごし方があります。
 恵方巻に入れる定番の具材は、縁起が良いとされている以下の7つの食材です。
恵方巻に入れる定番の具材は、縁起が良いとされている以下の7つの食材です。







 こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
みんなをおうちに招いてホームパーティーを開いてみたいけれど、準備を考えるとちょっと面倒・・・という方も多いのではないでしょうか?ちょっとした工夫やポイントを押さえれば、簡単絶品&おしゃれに楽しむことができます。
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
みんなをおうちに招いてホームパーティーを開いてみたいけれど、準備を考えるとちょっと面倒・・・という方も多いのではないでしょうか?ちょっとした工夫やポイントを押さえれば、簡単絶品&おしゃれに楽しむことができます。
 ホームパーティーで実際にどんな料理を作ったらいいかわからないという方のために、まずはメニュー決めのヒントや段取りのアイデアをご提案します。
ホームパーティーで実際にどんな料理を作ったらいいかわからないという方のために、まずはメニュー決めのヒントや段取りのアイデアをご提案します。






















 こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。
毎年、年末年始になると市場も休みのためスーパーなどのお店もお正月に休業するところが多くなっています。そのためか開いているお店でもいつもより高いお正月価格になっている場合があります。そんな年末年始の食事で困らないためにも、必要な食品は計画的に買っておくのがおすすめです。
こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。
毎年、年末年始になると市場も休みのためスーパーなどのお店もお正月に休業するところが多くなっています。そのためか開いているお店でもいつもより高いお正月価格になっている場合があります。そんな年末年始の食事で困らないためにも、必要な食品は計画的に買っておくのがおすすめです。
 師走に入り、クリスマスケーキの申し込みなど年末の準備が始まってきました。12月は1年の中でも出費が多い月です。また、食材などもクリスマス頃から高くなる傾向にあります。そこで今回はお得に年末年始の準備をするポイントをご紹介します。
師走に入り、クリスマスケーキの申し込みなど年末の準備が始まってきました。12月は1年の中でも出費が多い月です。また、食材などもクリスマス頃から高くなる傾向にあります。そこで今回はお得に年末年始の準備をするポイントをご紹介します。
 年末の年越しそばや、お正月のお雑煮やおせちなど食卓に欠かせない食材はたくさんあります。年末年始のお買い物準備や買い忘れのないように是非お役立てください。
年末の年越しそばや、お正月のお雑煮やおせちなど食卓に欠かせない食材はたくさんあります。年末年始のお買い物準備や買い忘れのないように是非お役立てください。
 年末年始は、親戚や仲間たちとも集まる機会が増えますので、すき焼きやしゃぶしゃぶ・焼肉といったごちそう需要も見込んでおきましょう!
年末年始は、親戚や仲間たちとも集まる機会が増えますので、すき焼きやしゃぶしゃぶ・焼肉といったごちそう需要も見込んでおきましょう!
 師走のなにかと忙しい時期だからこそ、まとめてたくさん購入できる業務用食材でネット注文しましょう!
師走のなにかと忙しい時期だからこそ、まとめてたくさん購入できる業務用食材でネット注文しましょう!


















 こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。
さて、日本のクリスマス料理といえば皆さんは、なにを思い浮かべますか?やっぱり定番のチキンと答える人が多いかもしれません。クリスマスを前にいざなにを用意するか迷ってしまいますよね。今回はクリスマス料理の由来から、子供が喜ぶ定番メニュー10選をご紹介しますので、是非ご参考にしてみてください!
こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。
さて、日本のクリスマス料理といえば皆さんは、なにを思い浮かべますか?やっぱり定番のチキンと答える人が多いかもしれません。クリスマスを前にいざなにを用意するか迷ってしまいますよね。今回はクリスマス料理の由来から、子供が喜ぶ定番メニュー10選をご紹介しますので、是非ご参考にしてみてください!
 知ってるようで知らない!はじめに、日本にクリスマスが伝わった歴史から学び、日本にクリスマス文化が広まったきっかけまでを一緒にみていきましょう。
知ってるようで知らない!はじめに、日本にクリスマスが伝わった歴史から学び、日本にクリスマス文化が広まったきっかけまでを一緒にみていきましょう。
 明治屋によってクリスマスが広まってからというもの、他の食品メーカーなどでも続々とクリスマス商品の売り出しが始まりました。現在の日本のクリスマスでは、チキンやケーキを食べるのが風習になっていますが、そもそも何故食べられるようになったのかご存知ですか?クリスマス料理においても全てアメリカやヨーロッパの影響だと思っている人は、少なくありません。ここでは、日本のクリスマス料理の由来を食品ごとに詳しくみていきましょう。
明治屋によってクリスマスが広まってからというもの、他の食品メーカーなどでも続々とクリスマス商品の売り出しが始まりました。現在の日本のクリスマスでは、チキンやケーキを食べるのが風習になっていますが、そもそも何故食べられるようになったのかご存知ですか?クリスマス料理においても全てアメリカやヨーロッパの影響だと思っている人は、少なくありません。ここでは、日本のクリスマス料理の由来を食品ごとに詳しくみていきましょう。
 クリスマスパーティーのメニューを、いざ用意するとなると迷ってしまう人が多いと思います。せっかくのクリスマスパーティーなので、子どもの喜ぶ顔がみたいですよね。そんな人のために、ここでは子どもたちが喜ぶクリスマスの定番メニュー9選をご紹介しますので、是非ご参考にしてみてください。
クリスマスパーティーのメニューを、いざ用意するとなると迷ってしまう人が多いと思います。せっかくのクリスマスパーティーなので、子どもの喜ぶ顔がみたいですよね。そんな人のために、ここでは子どもたちが喜ぶクリスマスの定番メニュー9選をご紹介しますので、是非ご参考にしてみてください。
 業務用スーパーだからこそ提供できる「飲食店でも扱うクリスマスメニュー」も取り揃えておりますので、是非ご利用ください。
業務用スーパーだからこそ提供できる「飲食店でも扱うクリスマスメニュー」も取り揃えておりますので、是非ご利用ください。



















